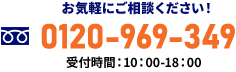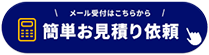【2025年最新】解体前の石綿(アスベスト)調査・除去で知っておくべき重要事項
2025年10月28日更新

みなさんこんにちは!徳島の解体専門業者のココカラ解体です。
「解体を検討している建物の石綿(アスベスト)はどうしたらいいの?」「法改正で何が変わったの?」そういった疑問や不安をお持ちではないでしょうか。石綿は、健康被害をもたらす非常に危険な物質であり、その解体・除去作業は法律で厳しく定められています。特に2021年以降、法律の改正が相次ぎ、「石綿の事前調査の義務化」や「罰則の強化」など、解体工事を行う全ての方にとって無視できない重要な変更がありました。この記事では、徳島市・阿南市で解体工事をお考えの皆様が、安全かつ法令を遵守して工事を進められるよう、「石綿 解体」に関する最新の重要事項を徹底的に解説します。この記事を読むと、最新の法改正で何が義務化されたのか、適切な事前調査の流れ、徳島地域で利用できる可能性のある補助金情報、そして安全な石綿除去の作業基準まで、解体工事を始める前に知っておくべき全てが分かります。特に、古い家屋の解体をご検討中のご家族はぜひ最後まで読んでみてください!
【2025年最新】解体前の石綿(アスベスト)調査・除去で知っておくべき重要事項
解体工事を安全かつ適法に進める上で、石綿(アスベスト)の問題は避けて通れません。私自身、徳島で長年解体工事に携わる中で、石綿に関するお客様の不安や戸惑いを数多く見てきました。特に最近の法改正によって、石綿の取り扱い基準は劇的に変わり、以前は対象外だった建材も規制の対象になっています。この変化を理解し、適切に対応することが、無用なトラブルやコスト増を避けるための鍵となります。
なぜ今、石綿(アスベスト)調査が必要?法改正のポイントを解説
石綿調査が今、なぜこれほどまでに重要視されているのか、その背景には「大気汚染防止法」や「石綿障害予防規則」の大きな改正があります。改正の最も重要なポイントは、建築物の解体・改修工事を行う際の石綿含有建材の「事前調査」が、規模に関わらず原則全ての工事で義務化されたことです。この改正は、過去に石綿の飛散による健康被害が社会問題化したことを受け、作業者だけでなく周辺住民の健康を守るために強化されました。具体的には、2022年4月から、解体工事の元請け業者には、石綿含有建材の有無について、工事の規模や請負金額に関わらず、事前に調査することが義務付けられています。また、調査結果の行政への報告義務も課せられており、違反した場合には罰則が適用されることになりました。
義務化対象が拡大!レベル3建材も規制対象に
これまでの石綿規制では、飛散性の高い「レベル1」や「レベル2」の建材が主に規制対象でしたが、2021年の法改正により、飛散性が比較的低いとされていた「レベル3」の建材についても、作業時の飛散防止対策や事前調査・届出の対象に明確に組み込まれました。レベル3建材とは、ビニル床タイルや石綿含有のボード類など、私たちの身の回りにある多くの古い建物に使われているものです。ココカラ解体が以前、築40年の木造住宅の解体をご依頼いただいた際も、屋根材や外壁の一部にレベル3の石綿含有建材が使われていました。このレベル3建材の規制強化は、石綿による健康被害を徹底的に予防するという国の強い意志の現れであり、解体業者として私たちも、より慎重な対応が求められています。お客様にとっては、以前なら調査対象外だった部分も調査が必要になり、調査コストが発生する可能性があるという点を理解しておく必要があります。
徳島市・阿南市で活用できる!石綿調査・除去の補助金・支援制度
石綿の調査や除去には、当然ながら費用が発生します。特に古い建物を所有されている方にとって、この費用負担は大きな懸念材料です。しかし、ご安心ください。石綿対策を推進するため、地方自治体によっては、その費用を軽減するための補助金制度を設けている場合があります。例えば、徳島市や阿南市においても、石綿の飛散による市民の健康被害を予防するため、「民間建築物石綿含有調査事業」や「石綿除去費補助事業」といった名前で、調査費用や除去費用の一部を助成する制度が実施されていることがあります。具体的な補助金額や申請条件は、年度や自治体の予算によって異なりますが、調査費用の上限25万円、除去費用の上限50万円など、まとまった金額が補助されるケースも少なくありません。補助金は申請期間や予算に限りがあるため、解体計画を立てる際には、まずココカラ解体のような地元の解体業者か、直接、徳島市役所や阿南市役所の担当窓口に確認してみることを強くお勧めします。
事前調査は「有資格者」が必須!安心・確実な調査の流れ
石綿の事前調査は、誰でもできる作業ではありません。2023年10月からは、解体工事の元請け業者または建物の所有者が、必ず「石綿調査者」や「特定石綿含有建材調査者」といった厚生労働大臣が定める講習を修了した有資格者に調査をさせることが義務付けられています。この有資格者による調査は、石綿の含有の有無を正確に判断し、その後の安全な除去計画を立てるための最初の一歩です。調査の流れとしては、まず設計図書などで石綿の使用履歴を確認する「書面調査」を行い、次に実際に建物を目視で確認する「現地調査」を実施します。怪しい建材が見つかった場合は、それを採取して分析機関で石綿の有無を確かめる「分析調査」に進みます。ココカラ解体では、提携の有資格者がこれらの調査を責任をもって行い、その結果を基に安全で適正な「石綿 解体」作業計画を策定します。
知らないと罰則も?解体工事における石綿除去の作業基準と記録の義務
石綿が検出された場合、解体工事は「石綿障害予防規則」に基づいた非常に厳格な作業基準に従って行わなければなりません。これは、作業者自身の安全確保と、石綿粉じんの外部への飛散を最大限に防ぐためです。たとえば、高レベルの石綿除去作業では、作業場所を完全に隔離し、負圧除じん装置で作業場内の空気を浄化しながら作業を進めます。また、作業者は高性能な防じんマスクや防護服の着用が義務付けられます。さらに、解体業者には、これらの作業の状況を写真や動画で記録し、作業完了後3年間保存する義務があります。この記録は、適正な石綿除去が行われたことの証明となり、万が一、周辺住民から健康被害に関する問い合わせがあった際の重要な証拠となります。この記録保存義務を怠った場合や、基準通りに作業を行わなかった場合には、行政指導や罰則が科される可能性があるため、信頼できる業者に任せることが極めて重要です。
まとめ
本記事では、解体工事における「石綿 解体」に関する最新の法改正のポイントから、事前調査の義務化、徳島地域での補助金の活用、そして安全な除去作業の基準までを詳しく解説しました。石綿の問題は複雑であり、法改正も頻繁に行われますが、最も重要なことは、2023年10月以降、有資格者による事前調査が必須となり、違反には罰則があるということです。古い建物の解体をご検討の方は、まず石綿の事前調査から始めることが、安全かつ適法に工事を進めるための第一歩となります。ココカラ解体では、徳島地域密着をモットーに、空き家、建て替え時の解体作業から土地活用のサポートまでおこなっております。是非!解体の事ならココカラ解体にお任せください!
<施工エリア>
〇徳島県徳島市、阿南市
〇その他徳島県全域